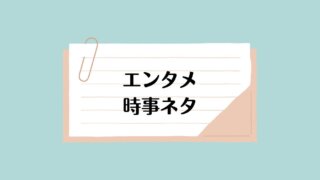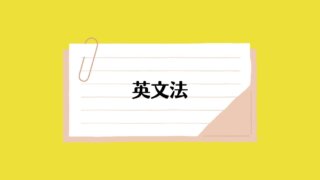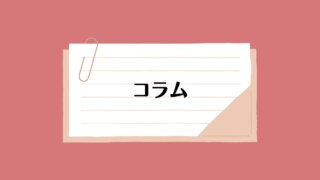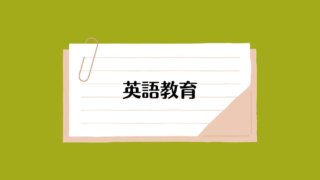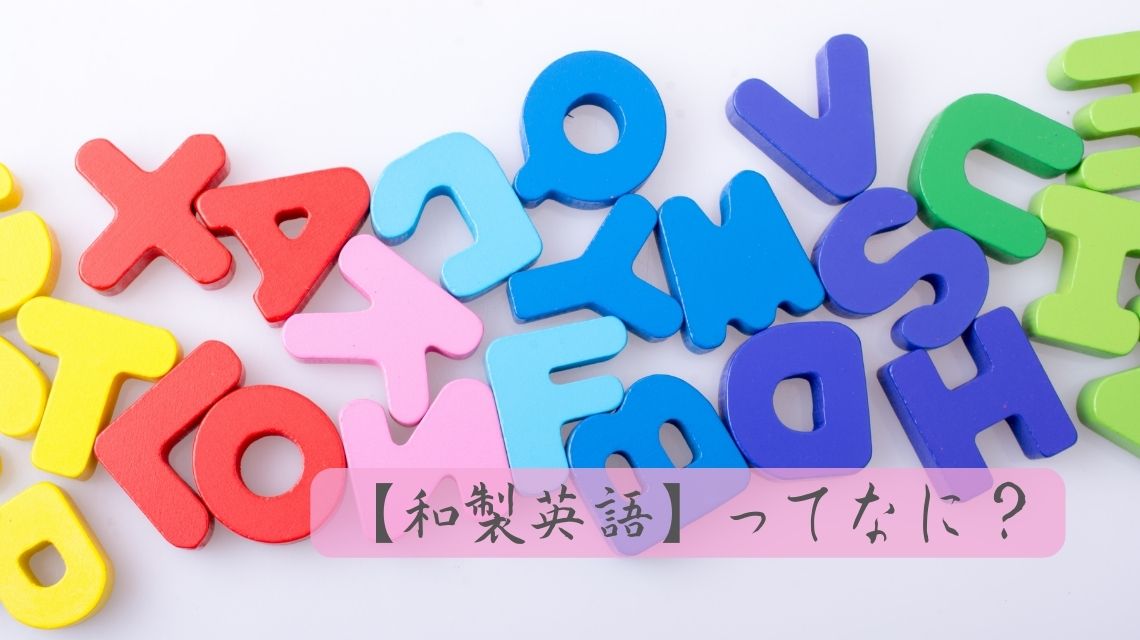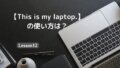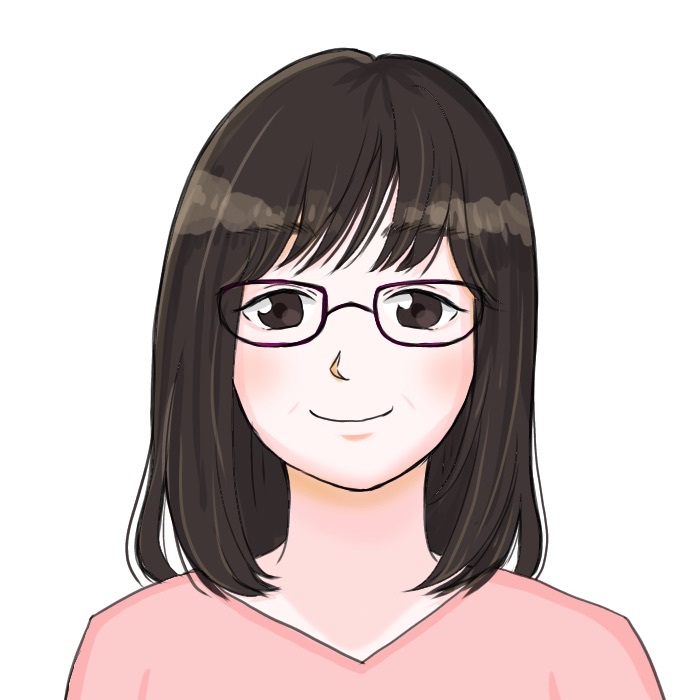
こんにちは。
今日は「和製英語」についてまとめてみました。
「和製英語」とは、日本だけで使われているカタカナ英語のこと。
カタカナで書かれているとアメリカやイギリスなどの英語圏でも通じる思ってしまいますが、実は日本以外ではまったく通じない言葉ってけっこう多いんですよ。
そこで今回は、「え?それも通じないの?」というような面白い和製英語を集めて解説してみました。

実は英語じゃない言葉って、Lesson12に出てきた「ノートパソコン」がそうなんですよね。
確か英語では「laptop」って言うんでしたっけ?
「パソコン」「ブラインドタッチ」は和製英語?
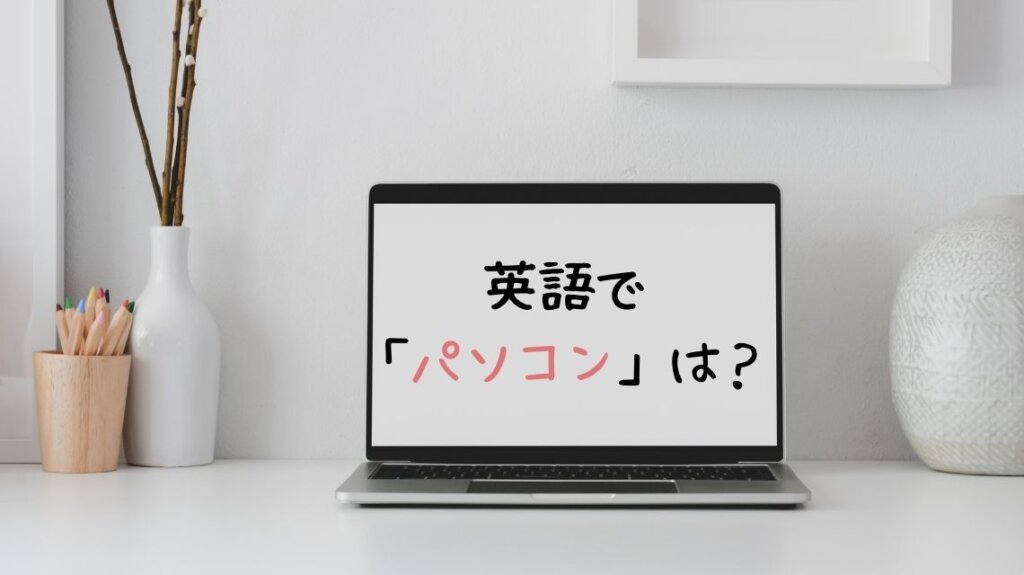
「ノートパソコン」という言葉は確かに和製英語です。
そして「パソコン」という言葉も、日本でしか通じない和製英語。
パソコン…personal computer, pc
デスクトップパソコン…desktop, desktop pc
英語で「パソコン」は「personal computer」またはそれを略して「pc」といいます。
そして持ち運べるノートパソコンに対して、机の上に固定して使うディスプレイとキーボードが分離したタイプのパソコンを日本語ではデスクトップ(パソコン)と言いますね。
「デスクトップ」はそのまま「desktop」や「desktop pc」などといいます。

パソコンと言えば、ぼく、ブラインドタッチが苦手なんですよねぇ。
不器用だから指の動きが遅いし、キーボードを見ながらでないと間違ってばかりで…。
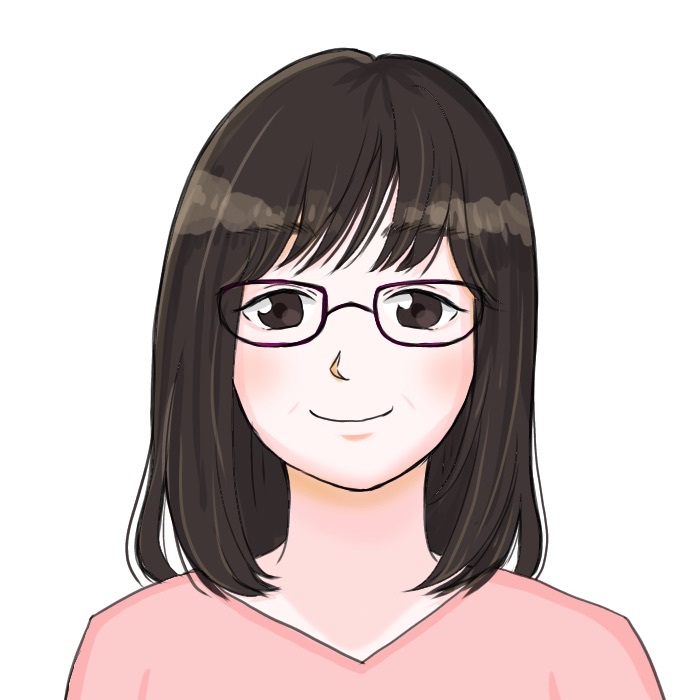
まぁ、それは各自で練習してください!
ところで「ブラインドタッチ」も実は和製英語だということを知ってます?
ブラインドタッチ…touch typing
「ブラインドタッチ」は英語では「touch typing」。
「touch」は「軽く手で触れる」、「type」は「タイプする」「タイプライターを打つ」という意味があるので、キーボードを(目で確認しないで)指で触れながら打つというような意味になります。
日本語の「ブラインドタッチ」を英語で綴ると「blind touch」となります。
「blind」は「目の不自由な」というような意味なので、キーボードを見ないで操作するという意味になりそうですよね。
しかし「blind touch」は英語圏では使われていない言葉です。
それだけではなく、最近は日本語でも「ブラインドタッチ」という言葉は使われなくなってきています。
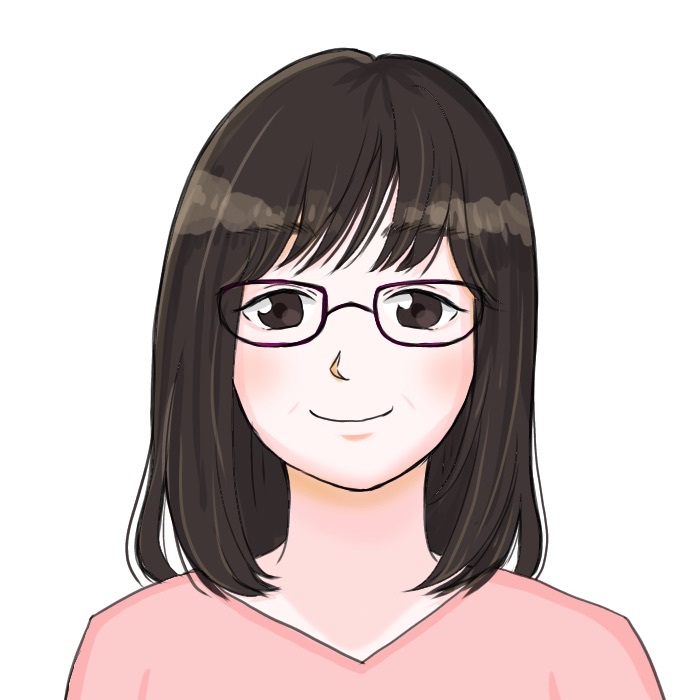
和製英語であるという以外に、「ブラインド」という言葉を使うことがあまり好ましくないという考えがあるようです。
なので、日本語でも「タッチタイピング」と表記することが増えてきていますよ。
「サラリーマン」や「OL」は和製英語?


そういえばこの前、
うちの父が外国の人に職業を聞かれた時、
「salary man(サラリーマン)」って答えたら
「??」って反応だったそうなんですよ。
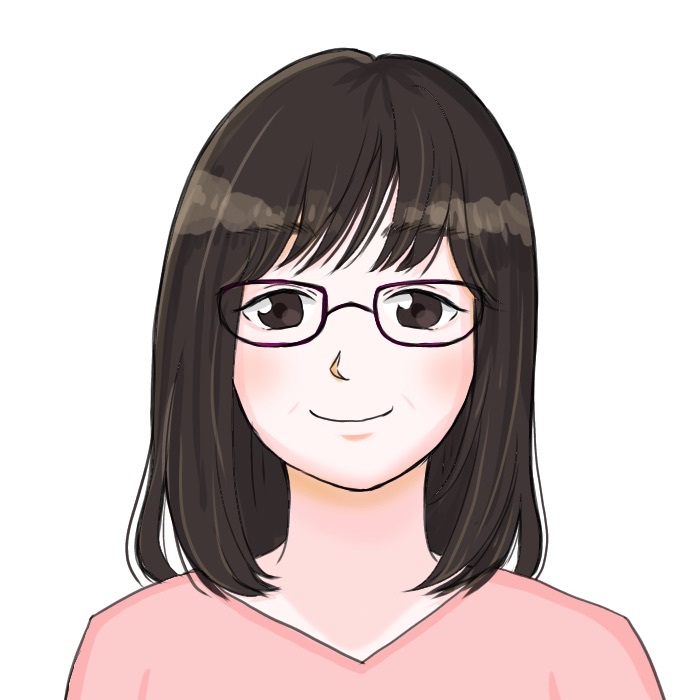
それは、「サラリーマン」や「オフィスレディ(OL)」が和製英語だからです。
「salary」には「給料」という意味があるので、
多くの日本人が普通に通用する英語だと思っているのではないでしょうか。

「サラリーマン」も和製英語なんですね…。
じゃあ、ひょっとすると父は、
「ビジネスマン」って答えればよかったんじゃないですか?
「salary man」は和製英語ですが、「business man」という英語は存在します。
しかし残念ながら「business man」には日本語で言う「サラリーマン」の意味はありません。
サラリーマン(OLも含む)…office worker
実業家、経営者…business man
「office」は「事務所」「オフィス」などの意味があります。
「worker」は「働く人」「労働者」という意味。
つまり「office worker」で「オフィスで働く人」=「サラリーマン」という意味になります。
「business」は「仕事」「事業」などの意味。

じゃあ、事務所で働いていない「サラリーマン」はなんて言えばいいんですか?
たとえば、友人はオフィスビルでは働いていますが、職種は「ガードマン」です。
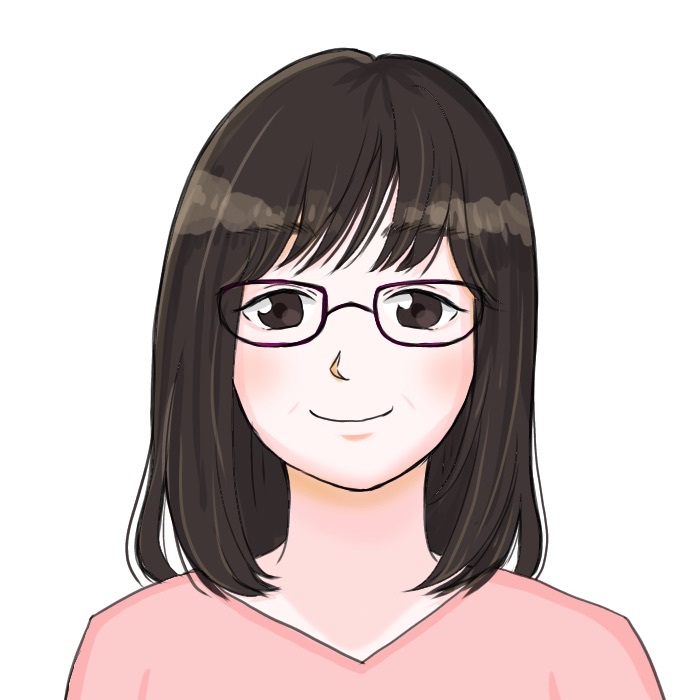
なるほど、それはいい質問だと思います。
実は英語では「サラリーマン」というようなざっくりしたとらえ方ではなく、
もっと、細かい職種に分けて考えることが多いんです。
ガードマン…security guard, guard
アルバイト、パート…part-time worker
テレビタレント…TV personality
職業に関する和製英語として「ガードマン」「アルバイト、パート」「テレビタレント」などがあります。
「security」は「安全」「警備」などの意味があります。
「guard」は「守衛」などの意味。
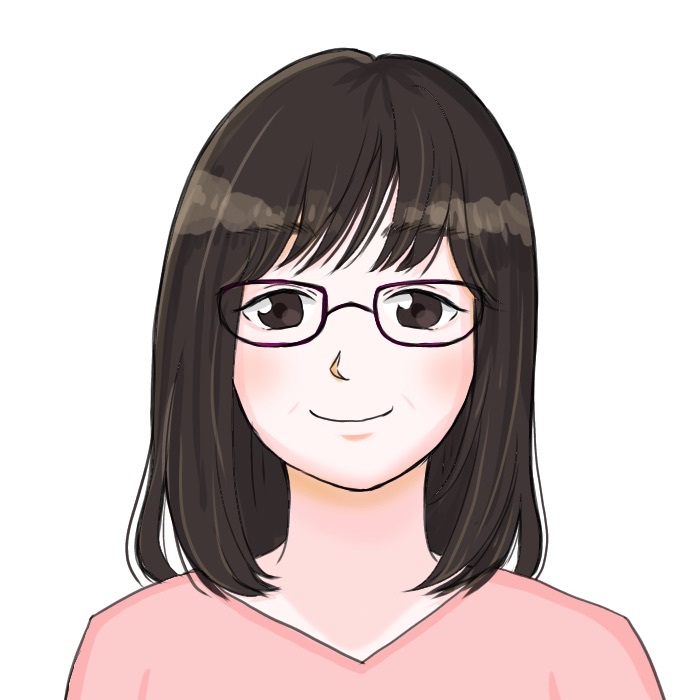
もしガードマンとして働いているお友達が職業を聞かれたら、
「I am a security guard.」
などと答えればいいですね。
「part-time」は「パートタイムの」「非常勤の」などの意味です。
「TV」は「テレビ」。
「personality」には「有名人」「タレント」などの意味があります。
「シャーペン」「ホチキス」「ホチキスの芯」は和製英語?
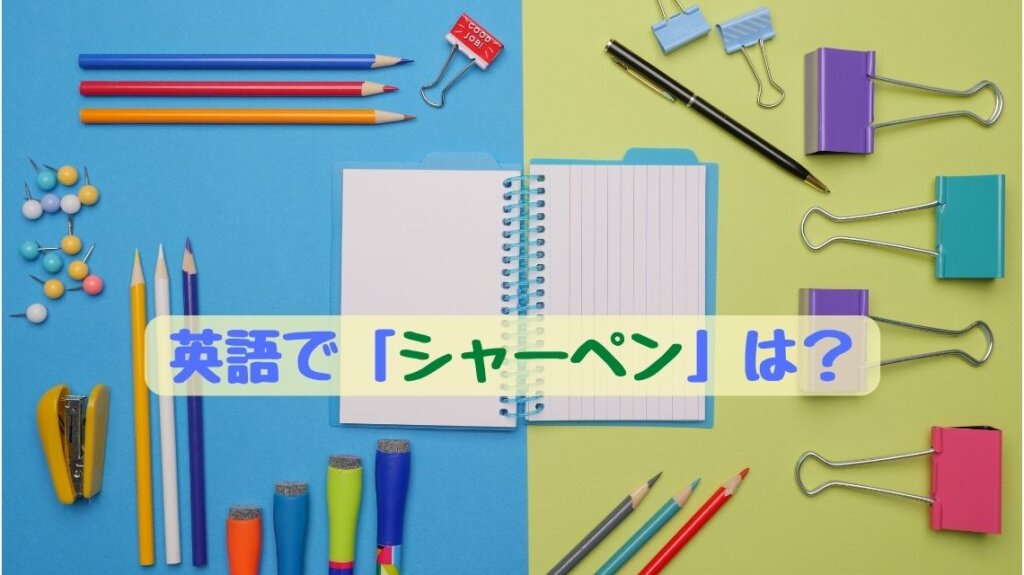

「シャーペン」ですか?
これは、かんたんですね。
ズバリ「シャープペンシル(sharp pencil)」じゃないですか?
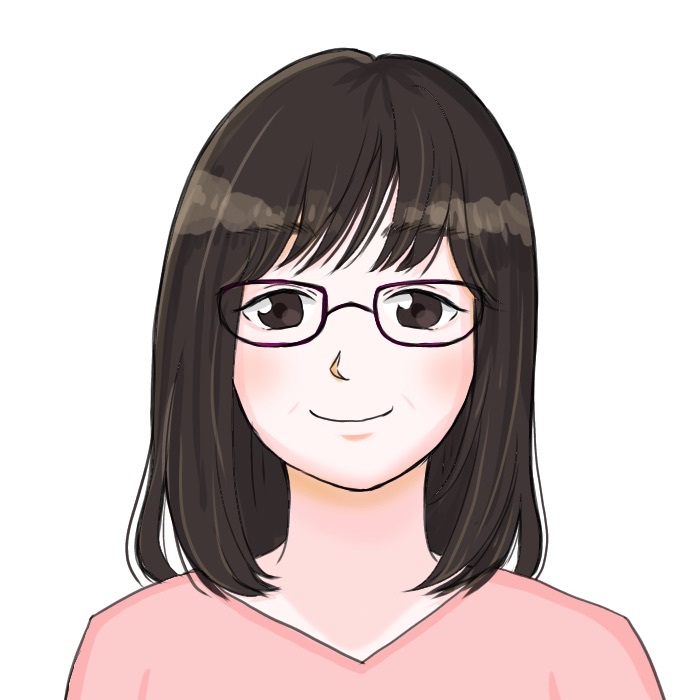
「シャーペン」が「シャープペンシル」を縮めたものだというところまでは正解。
しかし実は「シャープペンシル」という言葉が「和製英語」なんです。
シャーペン…mechanical pencil
「mechanical」には「機械の」「機械仕掛けの」などの意味があります。
確かにシャーペンは鉛筆とは違い機械的な操作で中から芯が出てきますね。
では、なぜ日本では「シャープペンシル」や「シャーペン」と呼ばれるようになったのでしょうか。
それは、アメリカで最初に発売されたシャーペンが「エバーシャープ(Eversharp)」という名前だったからだそうです。
「sharp」には「鋭い」などの意味があるため、芯のとがったシャーペンの外見とマッチしてしまったのでしょう。

シャープペンシルという言葉が和製英語だったんですね。
他にも文房具で和製英語はあるんですか?
ボールペン…ballpoint pen, biro
ホチキス…stapler
ホチキスの芯…staple
セロテープ…scotch tape, sellotape
ballpointの「point」には「先端」という意味があります。
つまり、「ballpoint」で先端がボール状のという意味になるので、「ballpoint pen」で「ボールペン」。
「biro」というのは「ボールペン」の意味でおもにイギリスで使われています。
これはボールペンの商品名がそのまま呼び名になったということです。
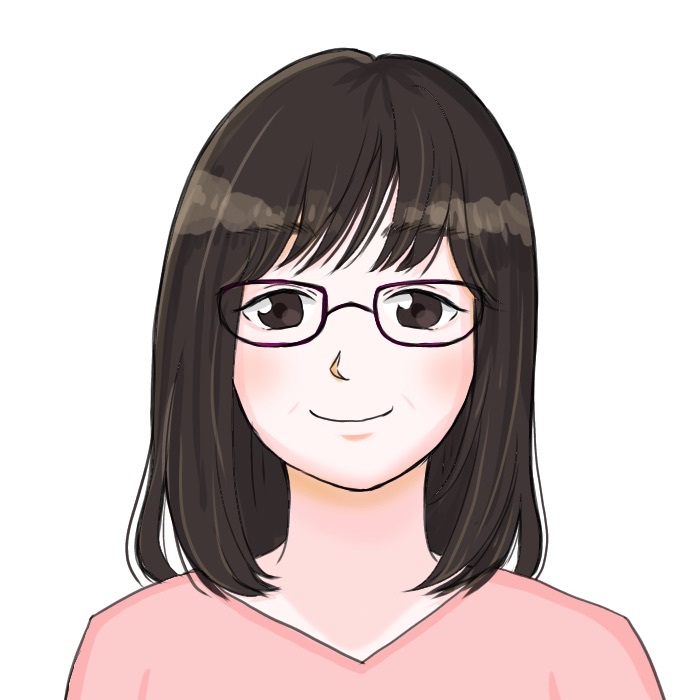
「ホチキス」は英語で「stapler」。
これも日本で普及した商品名が「ホチキス」だったので、
そのまま「ホチキス」と呼ぶようになったそうです。
ちなみに「ホチキスの芯」は「staple」といいます。
「セロテープ」はアメリカとイギリスで呼び方が違います。
アメリカでは「scotch tape」、イギリスでは「sellotape」。
どちらも商品名ですが、日本ではイギリス風の呼び方が広まったということですね。
今日のまとめ:「和製英語」

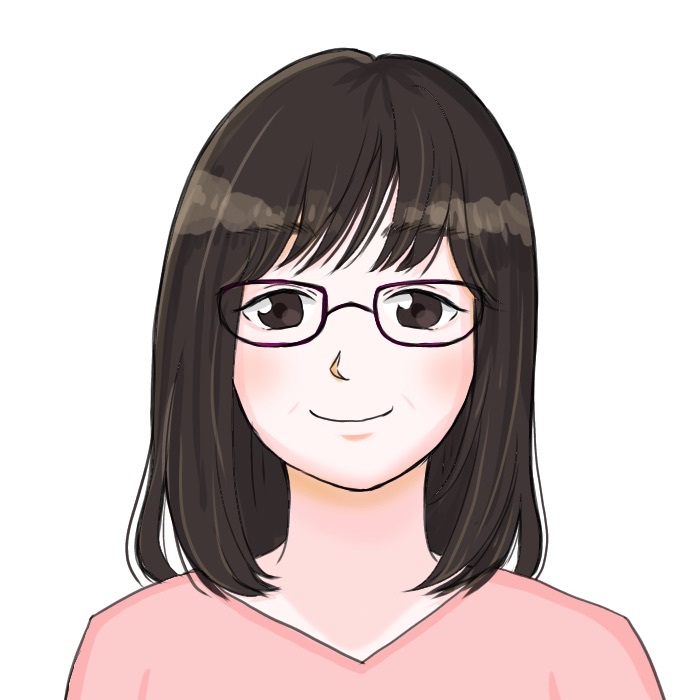
日本でのみ通用する和製英語についてまとめました。
ここに紹介した和製英語は、実はほんの一部にすぎません。
機会があったら、第2弾、第3弾…と続けていきたいと思っています。
カタカナで表記されているからといって、英語圏で通用するとは思わないようにしてください。
さもないと、
「I am a salary man.」
などという奇妙な英語を話してしまうことになるかもしれません。